クリップボードの内容を他のマックへ送る
アップルスクリプトをwebで調べていたら、クリップボードの内容を他のマックのクリップボードへ送る事が出来るのを知りました。ココです。
これは結構便利で、webのURLをコピーして他の起動中のマックへ転送するのに使っております。(以前はメッセンジャーソフトを使っていました。)
以下に、MacOS9と8.6上での私のやり方を書きます。セキュリティには十分注意してください。
クリップボード内容を送られる先のマックのコントロールパネルの「ファイル共有」の「開始/停止」のタブを選択して、プログラムリンクを「開始」して「プログラムリンクしています」状態にしてください。また「所有者の名前」と伏せ字ですが「所有者のパスワード」と「コンピュータの名前」を確認してください。次に「利用者&グループ」のタブを選択して、上記の所有者の名前のユーザ名を開き、そのユーザ名ウィンドウの「表示項目:共有」を選択して、「プログラムリンク」のチェックボックスをチェックします。(そのユーザにプログラムリンクの権限が与えられることを意味します。)
両方のマックのセレクタのAppleTalkが使用になっている事と、両方のマックのコントロールパネルの「AppleTalk」の経由先が使用しているネットワークになっている事も確認してください。(ファイル共有が出来ているマシン間なら大丈夫です。)
ここからアップルスクリプトです。送る側のマックの「スクリプト編集プログラム」(アプリケーションのApple エクストラのAppleScriptフォルダにあります。)で新規スクリプトを開き、下の内容を貼り付けて、4行目末尾の「"PB3400"」のPB3400を送られる先コンピュータの名前に替えてください。
on run
新規スクリプト「名称未設定」を保存する時は、名前(例:00ClipBordCopyPB3400)をつけて、「フォーマット:アプリケーション」を選択してから「保存」ボタンを押して保存しください。
なお、AppleTalkによる両方のマック間の接続が出来ていないと、「スクリプトファイルXXXはコンパイル出来ません。文書として保存しますか?」となりますので、両方のマックのAppleTalkと送られる先マックのファイル共有を再確認してください。(送られる先のマックの「ファイル共有」を「ファイル共有をしています」にして、送る側のマックの「セレクタ」で「AppleShare」を選択して送られる先コンピュータの名前が見えることを確認すると簡単です。)
使い方は、送る側マックのクリップボードに送りたい内容をコピーまたはカットして取り込みます。(コマンド+Cやコマンド+Xですね。)で、先ほどアプリケーションとして保存したスクリプトファイルを実行します。すると、場合によっては「キーチェーンアクセス」への許可と「所有者の名前」と「所有者のパスワード」が求められますので、入力してください。すると1秒+αで送る側マックのクリップボードの内容が送り先マックのクリップボードに入ります。送り先マックで貼り付け(コマンド+V)をすれば、終わりです。私はこのスクリプトファイルをアップルメニューに入れておくことで、簡単に起動できるようにしています。
これは結構便利で、webのURLをコピーして他の起動中のマックへ転送するのに使っております。(以前はメッセンジャーソフトを使っていました。)
以下に、MacOS9と8.6上での私のやり方を書きます。セキュリティには十分注意してください。
クリップボード内容を送られる先のマックのコントロールパネルの「ファイル共有」の「開始/停止」のタブを選択して、プログラムリンクを「開始」して「プログラムリンクしています」状態にしてください。また「所有者の名前」と伏せ字ですが「所有者のパスワード」と「コンピュータの名前」を確認してください。次に「利用者&グループ」のタブを選択して、上記の所有者の名前のユーザ名を開き、そのユーザ名ウィンドウの「表示項目:共有」を選択して、「プログラムリンク」のチェックボックスをチェックします。(そのユーザにプログラムリンクの権限が与えられることを意味します。)
両方のマックのセレクタのAppleTalkが使用になっている事と、両方のマックのコントロールパネルの「AppleTalk」の経由先が使用しているネットワークになっている事も確認してください。(ファイル共有が出来ているマシン間なら大丈夫です。)
ここからアップルスクリプトです。送る側のマックの「スクリプト編集プログラム」(アプリケーションのApple エクストラのAppleScriptフォルダにあります。)で新規スクリプトを開き、下の内容を貼り付けて、4行目末尾の「"PB3400"」のPB3400を送られる先コンピュータの名前に替えてください。
on run
-
global aClip
set aClip to the clipboard
tell application "Finder" of machine "PB3400"
-
activate "Finder"
delay 1
set the clipboard to aClip
新規スクリプト「名称未設定」を保存する時は、名前(例:00ClipBordCopyPB3400)をつけて、「フォーマット:アプリケーション」を選択してから「保存」ボタンを押して保存しください。
なお、AppleTalkによる両方のマック間の接続が出来ていないと、「スクリプトファイルXXXはコンパイル出来ません。文書として保存しますか?」となりますので、両方のマックのAppleTalkと送られる先マックのファイル共有を再確認してください。(送られる先のマックの「ファイル共有」を「ファイル共有をしています」にして、送る側のマックの「セレクタ」で「AppleShare」を選択して送られる先コンピュータの名前が見えることを確認すると簡単です。)
使い方は、送る側マックのクリップボードに送りたい内容をコピーまたはカットして取り込みます。(コマンド+Cやコマンド+Xですね。)で、先ほどアプリケーションとして保存したスクリプトファイルを実行します。すると、場合によっては「キーチェーンアクセス」への許可と「所有者の名前」と「所有者のパスワード」が求められますので、入力してください。すると1秒+αで送る側マックのクリップボードの内容が送り先マックのクリップボードに入ります。送り先マックで貼り付け(コマンド+V)をすれば、終わりです。私はこのスクリプトファイルをアップルメニューに入れておくことで、簡単に起動できるようにしています。
対応OSについて:スクリプト6行目の「delay」は動作を確実にするために入れてあります。MacOS 8.5
以降でないと使えないそうなので、OS8.1以前の環境で使う場合は6行目を外して試みてください。
ご参考にどうぞ
「AppleTalkのつなぎかた」
「ファイル共有の方法」(トップページはこちら)
「AppleScript(アップルスクリプトの説明)」
「ネットワーク経由のAppleScript」
ご参考にどうぞ
「AppleTalkのつなぎかた」
「ファイル共有の方法」(トップページはこちら)
「AppleScript(アップルスクリプトの説明)」
「ネットワーク経由のAppleScript」
Color StyleWriter 2200 + StyleWriter EtherTalkアダプタ
 1995年発売のアップル純正(Canon製)モバイルインクジェットプリンターです。2003年にデッドストック品を購入しました。蓋を閉めておけばコンパクトになり埃も入りません。白黒なら画質的に問題なく、サードパーティの瓶入りインクによるインク補充でランニングコストは抜群です。給紙機構の働きに悪い評判のある機種ですが、裏のネジを外して、爪で止められた筐体を開き、給紙ローラー等のゴム部品を水で掃除したところ、うまく動いております。些細な欠点として、ある程度時間が経つと自動的に電源がOFFになるのが余計なお世話に感じられます。付属フォントを活かして馬鹿張り紙を作ることもあります。
1995年発売のアップル純正(Canon製)モバイルインクジェットプリンターです。2003年にデッドストック品を購入しました。蓋を閉めておけばコンパクトになり埃も入りません。白黒なら画質的に問題なく、サードパーティの瓶入りインクによるインク補充でランニングコストは抜群です。給紙機構の働きに悪い評判のある機種ですが、裏のネジを外して、爪で止められた筐体を開き、給紙ローラー等のゴム部品を水で掃除したところ、うまく動いております。些細な欠点として、ある程度時間が経つと自動的に電源がOFFになるのが余計なお世話に感じられます。付属フォントを活かして馬鹿張り紙を作ることもあります。マックファンの方からStyleWriter EtherTalkアダプタという珍しい物を譲ってもらったので、LANで繋がっている事実上全ての所有マックから使えるようになりました。ただ何故かswitching HUBと相性が悪く、dumb HUBを噛ませてあります。 無線iBook等からも印刷できるので快適です。
PLUS PIANOプロジェクターによるホームシアター

HosukeFilmにはプラスビジョン社の「PIANO」(ピアノ)というビデオプロジェクターを使ったホームシアターがあります。上の写真は上映中の状態です。右が潜水艦映画の映像の一部で、左が開いた扉を通して見える隣の部屋です。
 PIANOの技術的特徴はDLP方式と呼ばれる848x600=508800枚の可動鏡によって構成されたDLP素子という物で絵を表示する事にあります。透過液晶による通常のプロジェクターと較べて黒がクッキリと出て、ドットの格子も目立ちません。
PIANOの技術的特徴はDLP方式と呼ばれる848x600=508800枚の可動鏡によって構成されたDLP素子という物で絵を表示する事にあります。透過液晶による通常のプロジェクターと較べて黒がクッキリと出て、ドットの格子も目立ちません。また、商品コンセプトとして映画フィルムの正確な再現に重点がおかれているのも気に入っている点です。逆にテレビ(ビデオカメラ撮影)映像はイマイチです。
映画フィルムの再現を具体的に書くと、強調の無い自然な発色と階調描写です。他のプロジェクターやテレビでは見栄えを良くするために色や輪郭等を強調している場合が多いです。
かなり小形軽量(2kg)なので天井への設置は簡単です。左の写真の左上にある黄色い物体がプロジェクタです。自転車のゴム縄で天井部に張り付くようにしてあり、自転車カゴ用の網で万が一の落下を防いでおります。
MOMITSU社のV880というマルチプレーヤとデジタル接続しているのでノイズも出ません。秋葉原の「コンピュエース」という店では私の使っている5mのDVI規格ケーブル等、各種ケーブルが安く購入出来ます。
 スクリーンはOS社の業務用を使っております。幅1800mm長さ1800mmのホワイトを使用しております。巻き取り部が無骨で大きめですが、ホームシアター用スクリーンより随分安いです。スクリーン表面は家庭用と同じです。
スクリーンはOS社の業務用を使っております。幅1800mm長さ1800mmのホワイトを使用しております。巻き取り部が無骨で大きめですが、ホームシアター用スクリーンより随分安いです。スクリーン表面は家庭用と同じです。プロジェクタとスクリーンの距離は大体2.6m位で、6畳間の短辺でも約90インチサイズの上映が可能です。ただし観る位置も壁際になります。(距離が近すぎると視角が広くて疲れます。)
プロジェクタのテレビに対する欠点は部屋を暗くしなければならないことですが、部屋を暗くして潜水艦映画Uボートを観ていると、狭い艦内に居る気分になります。ただし見終わってから部屋を明るくしても気分はしばらく戻りません。(HosukeFilmは非常に狭いのです。)
OLYMPUS OM SYSTEM
 2004年暮れ、銀座で古いビルディングが壊されることを知り、写真に残しておきたく思い、数年ぶりに銀塩スチルカメラを使いました。
2004年暮れ、銀座で古いビルディングが壊されることを知り、写真に残しておきたく思い、数年ぶりに銀塩スチルカメラを使いました。オリンパスOM3Ti(写真ではZuiko24mmF2.8を装着)というカメラの操作フィーリングの良さと、レンズの写りに感心しました。
恥ずかしながらフィルムは1999年に入れたコダクローム64です。変色しておりましたが、取り込み時に補正してあります。下の廃墟の写真は1999年撮影です。

銀座 可口飯店(コカレストラン) 24mmF2.8(絞り開放)

某アパート 50mmF1.2(絞り値失念)
SONY Cybershot U10
 ソニーのとても小さなデジカメU10です。前面面積の小ささと、メロウパールピンクという色は、構えていても警戒されにくいです。画質はそれなりですが、素早い動作と簡潔で優れた操作性が特徴です。マクロ撮影も出来ます。現在は予備機として常時カバンに入っております。
ソニーのとても小さなデジカメU10です。前面面積の小ささと、メロウパールピンクという色は、構えていても警戒されにくいです。画質はそれなりですが、素早い動作と簡潔で優れた操作性が特徴です。マクロ撮影も出来ます。現在は予備機として常時カバンに入っております。KONICAMINOLTA DiMAGE A200とCONTAX i4R
 左のコニカミノルタ Dimage A200はレンズ性能(28mmF2.8〜200mmF3.5)が良い割には小型軽量で、強力な手振れ防止機能と相まって主力デジカメになっております。一眼レフに迫る画質で地味ながらも忠実な発色も気に入っております。
左のコニカミノルタ Dimage A200はレンズ性能(28mmF2.8〜200mmF3.5)が良い割には小型軽量で、強力な手振れ防止機能と相まって主力デジカメになっております。一眼レフに迫る画質で地味ながらも忠実な発色も気に入っております。右のコンタックスi4RはSONY U10を若干大きくした程度のサイズですが、400万画素で動画性能も優れているので常時携帯しております。
どちらもメーカーがデジカメ撤退を表明して安くなった所をハイエナ買いしました。
NIKON COOLPIX S10
 しっかり撮るためのDimage A200と常に携帯しているi4R、どちらも気に入っておりますが、自由な角度で楽に撮れる小型スイバルデジカメを試したく実質22000円で購入しました。
気楽に
ウェストレベルで撮影出来たり、10倍超望遠でも手振れ補正がよく効きます。このカメラ、AF速度が遅く、マニュアル操作がしづらい等、欠点も多いのですが、
スイバルというのは背面固定液晶、可変液晶と別次元の便利さです。(理想的デジカメ形態です。) 敢えて言えば縦位置撮影は少々悩みますが。
しっかり撮るためのDimage A200と常に携帯しているi4R、どちらも気に入っておりますが、自由な角度で楽に撮れる小型スイバルデジカメを試したく実質22000円で購入しました。
気楽に
ウェストレベルで撮影出来たり、10倍超望遠でも手振れ補正がよく効きます。このカメラ、AF速度が遅く、マニュアル操作がしづらい等、欠点も多いのですが、
スイバルというのは背面固定液晶、可変液晶と別次元の便利さです。(理想的デジカメ形態です。) 敢えて言えば縦位置撮影は少々悩みますが。
E-mail:yy_20th$$$yahoo.co.jp($$$->@)、または下のGuestbookにどうぞ。
 私(HosukeFilmアシスタント)のマック所有歴は1999年からと短いのですが、マック愛好家を自称しております。で、数あるマックのなかでも、一番好きなのは? と直感的に考えた結果、この機種について書くことにしました。
私(HosukeFilmアシスタント)のマック所有歴は1999年からと短いのですが、マック愛好家を自称しております。で、数あるマックのなかでも、一番好きなのは? と直感的に考えた結果、この機種について書くことにしました。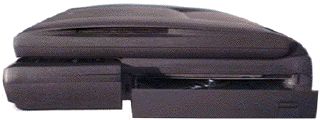 PB5300とPB3400のデザイナーの話を見つけたのでリンクを付けておきます。
PB5300とPB3400のデザイナーの話を見つけたのでリンクを付けておきます。 最後にPowerBook3400がノートパソコンとしてのサイズを犠牲にしてまでこだわって搭載しているウーハ付きスピーカシステムの感想を述べます。
最後にPowerBook3400がノートパソコンとしてのサイズを犠牲にしてまでこだわって搭載しているウーハ付きスピーカシステムの感想を述べます。